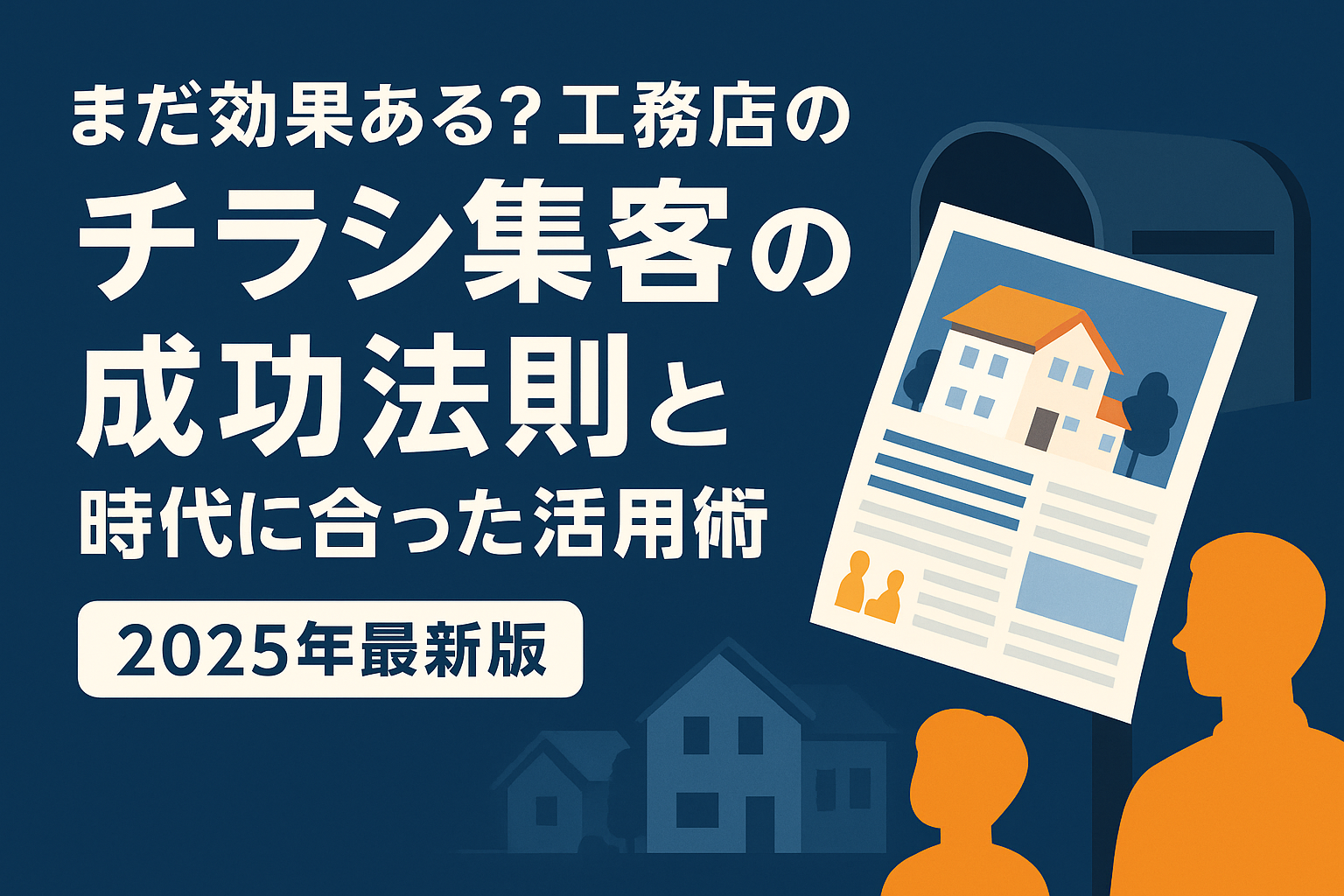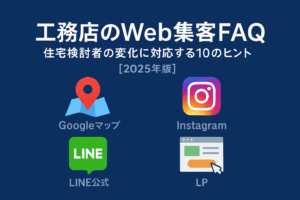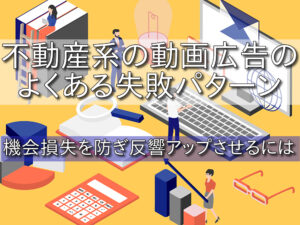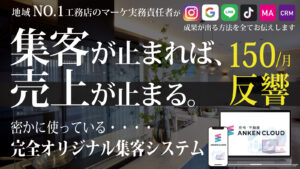チラシは“時代遅れ”ではない
「最近はSNSやWeb広告が主流で、チラシなんてもう効果がないのでは?」
住宅業界や広告代理店の現場で、そんな声を耳にすることが増えました。確かに、スマホが生活の中心となり、若年層を中心に紙媒体を目にする機会は減っています。しかし、地域密着型の工務店にとって、チラシは今なお“来場・資料請求”などの成果を生む有効な手段です。実際、国土交通省が公表している住宅取得者の情報収集手段に関するデータでは、「紙のチラシ」から来場・問い合わせをした人の割合は20%以上。地域や年代によっては、Web以上の効果を発揮するケースもあるのです。
本記事では、チラシ集客の現状を正しく捉え、2025年の住宅購入者の動向に合わせた「成果の出るチラシの作り方・配り方」を、実例や戦略を交えて徹底解説します。
チラシに関する“思い込み”を一度リセットし、集客戦略の再構築に役立てていただければ幸いです。
今でも“チラシ”が集客に使われる3つの理由
「チラシはもう効果が出ない」「紙の広告にお金をかけるのは無駄」といった意見がある一方で、今でも月に数十件の来場や資料請求をチラシ経由で獲得している工務店は少なくありません。
なぜ、デジタル全盛の時代に、あえてチラシなのか?その理由は主に以下の3つです。
デジタルでは届かない層にアプローチできる
注文住宅や建売住宅を検討しているすべての人が、SNSやネット広告を見ているわけではありません。
特に以下のような層にとって、紙のチラシは今でも有力な情報源です。
- 40代〜60代の一次取得層・親世代
- インターネットやSNSに不慣れな世帯
- 地元に長く住んでいる年配層(親と同居を考える子世帯など)
新聞折込やポスティングは、こうした“ネットで情報を探さない層”にもリーチできるため、他の集客施策では取りこぼしてしまう見込み客を拾える手段でもあります。
地域密着型の販促にフィットしている
チラシの最大の強みは、「配布エリアを指定できること」です。
たとえば、半径3km以内に新しい住宅地ができた場合、その周辺にピンポイントで情報を届けることができます。また、チラシは地元感や親しみやすさを演出しやすい媒体でもあります。
「○○小学校区で新築を検討中の方へ」
「地域密着30年、○○町の暮らしを知り尽くしたスタッフが対応します」
といったキャッチコピーやストーリーは、Web広告では表現しづらい“地域密着”の魅力を伝えるのに効果的です。
来場や問い合わせにつながる導線設計が可能
紙のチラシをただ配るだけでは、効果は期待できません。しかし、適切なターゲット設定・訴求・導線設計ができれば、Web広告よりも反応率が高いことも珍しくありません。
たとえば、以下のような工夫で効果を最大化できます。
- モデルハウスイベントの案内+Web予約フォームへのQRコード
- 無料間取り相談・土地相談会の案内
- チラシ限定キャンペーンやプレゼント企画
これらをチラシ内でわかりやすく伝えることで、「とりあえず見に行ってみようかな」と思わせるきっかけを生み出せます。実際に、チラシからWebフォームに誘導して予約を受け付けた工務店では、来場予約率が3倍以上に増加した例もあります。
失敗するチラシ集客の典型パターン
チラシによる集客で成果が出ないとき、単に「紙の時代は終わった」と決めつけてしまいがちです。しかし、多くの場合、その失敗は“やり方”に原因があります。
ここでは、工務店が陥りがちなチラシ集客の失敗例を、3つの観点から整理してご紹介します。
安売り一辺倒の訴求で「価格競争」に巻き込まれる
多くの失敗例で最も多いのが、「価格」しか伝えていないチラシです。
- 「月々○万円でマイホーム!」
- 「今だけ大幅値引きキャンペーン!」
- 「限定3棟、最終値下げ!」
これらは一見魅力的に見えますが、価格だけを打ち出すと、競合との差別化ができず、“安さ合戦”に巻き込まれるリスクが非常に高くなります。さらに、価格で釣っても、その後の商談で失望されるケースも少なくありません。購入者は金額だけで家を決めるわけではなく、住宅の品質、暮らしのイメージ、アフターサポート、土地の魅力など、さまざまな視点から判断しているからです。
失敗を避けるには、価格訴求ではなく、「暮らしの豊かさ」や「家づくりの考え方」などの“価値訴求”を優先すべきです。
情報過多・デザイン崩壊で“読む気”を失わせる
いくらチラシに内容を詰め込んでも、読まれなければ意味がありません。
チラシが読まれない典型例として、
- 写真が小さく、文字だらけ
- 文字サイズが不揃い、見出しが目立たない
- 配色が多すぎてゴチャゴチャしている
- 何が“言いたいこと”なのかが一目でわからない
といった「読みづらさ」があります。
特に工務店の場合、「これも伝えたい、あれも載せたい」と情報を盛り込みすぎて、視覚的に“情報が渋滞”している状態になりがちです。情報は、少ない方が伝わります。チラシは、すべてを説明する場ではなく、興味を持たせて“次のアクション”へと誘導するツールだと割り切りましょう。
ターゲット・配布エリア・タイミングの戦略がない
チラシを「とりあえず配る」だけで終わっていませんか?
たとえば、
- 住宅を建てられない地域に大量配布
- 建築ニーズが少ないエリアに集中投下
- 入学・進学などのライフイベント期を外して配布
- 分譲地の完成時期と合っていない
など、「誰に・いつ・どこに届けるか」の設計が甘いことで、大きな無駄が発生しているケースがあります。
また、「ファミリー層向けの注文住宅」のチラシを、独身世帯の多いエリアに配布しても、効果は期待できません。成功するチラシは、「誰に届けたいのか(ターゲット)」「どのタイミングで届くべきか(配布時期)」「どのエリアがニーズがあるか(商圏分析)」がしっかり戦略に組み込まれています。
チラシからの“導線”が設計されていない
せっかくチラシを手にとってもらっても、問い合わせや来場につながる“次のアクション”が明確でなければ、成果は出ません。よくある例としては、
- 「見学予約はこちら」だけで連絡先が電話番号のみ
- QRコードがない、あるいはどこに飛ぶかわかりにくい
- WEBサイトに誘導しても、対象の物件ページに直接遷移しない
といった「導線設計の弱さ」です。
現代のユーザーは、“手間”に非常に敏感です。QRコード1つで完結するなら申し込むが、「電話してください」では離脱されるのが現実。
チラシは、“読む→行動する”までを1つの流れで設計する必要があります。紙からデジタルへの橋渡しができているかどうかが、成果に直結します。
「チラシが悪い」のではなく「使い方」が間違っている
チラシ集客がうまくいかない最大の理由は、「紙媒体だから効果がない」のではなく、“戦略なき配布”になっているからです。
何を伝えるのか(価値)
誰に届けるのか(ターゲット)
どこで反応を取るのか(導線)
これらを設計せず、ただチラシを撒くだけでは、費用対効果は見込めません。
成果が出るチラシの企画・制作とは?
失敗パターンの多くは「チラシそのものの設計が甘い」ことに起因しています。
では、反対に成果を出している工務店は、どのようにチラシを企画し、制作しているのでしょうか?
ここでは、成果の出るチラシに共通する考え方と、実際に取り入れるべき制作ポイントを紹介します。
成果が出るチラシの企画設計のポイント
成果を出すためのチラシ企画は、以下の5つの観点から設計されます。
1)目的を明確にする
「このチラシで何をしてもらいたいか」を明確にします。
- 来場予約を獲得したい
- 資料請求を促したい
- 建売の成約を目指す
- 認知拡大をしたい
目的によって、構成・ビジュアル・キャッチコピーの内容もまったく変わってきます。
目的を明確にしないまま制作を進めると、メッセージがぶれて成果につながりません。
2)ターゲットを絞る
「誰に向けたチラシか?」を明確にしましょう。
- 30代前半の共働き夫婦
- 40代の子育て中ファミリー
- 親との同居を検討している世帯
- 二世帯住宅を希望する人
など、ペルソナ(具体的な人物像)を想定し、その人が反応しやすい内容を盛り込みます。
たとえば、共働き夫婦には「家事ラク動線」や「共働き目線の収納提案」、二世帯希望者には「完全分離型」「親世代にも優しいバリアフリー設計」など、それぞれ訴求ポイントが異なります。
3)導線を最初に決める
チラシを手に取った人が、「次にどうすればいいか」が一目でわかるようにします。
- モデルハウス見学予約QRコード
- 電話番号と受付時間
- 「チラシを見た」と言えば〇〇プレゼント
など、アクションを明確に提示し、行動のハードルを下げる工夫が必要です。
フォームに直接遷移するQRコードや、LINE公式アカウントへの導線を用意すると、スマホ利用者の反応率が格段に向上します。
4)メインビジュアルで惹きつける
チラシは、一目見たときの“印象”でほぼ決まります。
- 注文住宅であれば外観写真やLDKの開放感が伝わる写真
- 建売住宅であれば間取り図+生活動線の紹介
- 家族の笑顔が伝わる写真や暮らしの様子
など、視覚的に「この家、素敵!」と思わせる構成が重要です。
また、建築パースや外観CGだけでなく、実際の暮らしがイメージできるよう、
リアルな生活感を感じさせる要素(家具・家族・照明)も大切です。
5)キャッチコピーと見出しで反応率を決める
キャッチコピーは、読まれるかどうかを決める“最初のフック”です。
成功しているチラシでは、以下のような暮らし視点・地域密着・限定性のあるコピーが多用されています。
- 「○○小学校区で、のびのび子育てできる家、できました。」
- 「共働き夫婦に選ばれる“家事ラク設計”見学会開催」
- 「先着5組限定|土地+建物の相談フェア開催」
重要なのは、「誰に何を伝えるか」を一目でわかるようにすることです。
見出しや構成も、縦読みだけで内容がざっくり伝わるように意識して設計しましょう。
成果の出たチラシ事例(2選)
事例①:賃貸ポスティング×Instagram広告×QUOカード

【企画趣旨】
30 代後半から 40 代のファミリー層向けの生活の質を大切にし、家族と共に安心・快適に暮らせる家を求めている方向けの平家イベントとして企画。
【手段】
賃貸ポスティング 6 万部 インスタ広告 45,000 円 ノベルティ(QUO カード)
【成果】
来場者数:16組 (来場単価 39,687 円) 契約:2 組(契約単価 317,500 円)
事例②:賃貸ポスティング×Instagram広告×ノベルティ

【企画趣旨】
注文住宅の初期検討(土地探しから)を行っているお客様を対象に、キャンペーンを活用してお得に住まいづくりを進めたい方を集客。土地バンクを使っているので土地情報をたくさん公開するという企画です。
【手段】
賃貸ポスティング 4 万部 インスタ広告 100,000 円ノベルティ(QUO カード、化石発掘、トミカ釣りなど)【成果】
来場者数:46組 (来場単価 17,826 円)契約:4組(契約単価 205,000 円)
このように、成功しているチラシは“感覚”ではなく、“戦略的に設計”されている点が共通しています。
2025年の住宅検討者の変化とチラシ戦略のアップデート
チラシは「古い手法」だと思われがちですが、ターゲットの行動変化に合わせて進化させれば、今でも十分に成果を出せる媒体です。住宅購入検討者の思考や行動がどのように変化しているのか、そしてその変化に対応するチラシ活用のアップデート戦略を解説します。
情報収集は「紙+デジタルのハイブリッド」が基本に
国土交通省の「住宅市場動向調査」によると、住宅購入を検討する際の情報収集経路は以下の通りです:
- インターネット:80.9%
- チラシ・パンフレット:56.3%
- モデルハウス:43.2%
- SNSや動画メディア:26.5%
(※出典:令和5年度 住宅市場動向調査/国土交通省)
このデータから分かるように、紙媒体は「最初の接点」や「詳細確認」のために依然として高い比率で利用されています。特に地方やシニア層では、チラシがきっかけになるケースが今も少なくありません。
ただし、注意すべきは、紙だけで完結しないという点です。
読者の行動は、「チラシで知る → Webで検索 → SNSで口コミ確認 → 比較 → 問い合わせ」
というプロセスに変化しています。
つまり、チラシは入口として有効であり、そこから“デジタルに接続する導線”を持たせることが成功の鍵となります。
比較検討が当たり前の時代に
2020年以降、家づくりにおける「比較検討」が格段に増加しています。
背景には以下の変化があります。
- スマホ普及による情報の非対称性の解消
→ どの住宅会社もネットで比較される時代に。 - 口コミ文化の浸透
→ SNSやYouTubeなどでの「リアルな声」が意思決定に影響。 - ライフスタイルの多様化
→ 自分の理想を叶えてくれる会社をじっくり探す傾向が強まった。
このような中で、チラシでも「売り込み」ではなく「比較される前提の設計」が求められています。
つまり、「選ばれる理由」を明確に提示しなければ、すぐに候補から外されてしまうのです。
「今すぐ客」だけでなく「これから客」への訴求が重要
住宅購入は、即決されるものではありません。
実際、住宅支援機構の調査では、住宅検討期間は平均で6ヶ月〜1年以上とされており、いわゆる「検討中・情報収集段階」の層が最も大きいといえます。
ここで重要なのが、チラシで「今すぐ建てたい人」だけに絞らない訴求を行うことです。
たとえば、
- 「失敗しない土地探しのポイント」
- 「家づくりを始める前に知っておくべき5つのこと」
- 「ローンや補助金、わかりやすく解説します」
など、“これから家づくりを考える人”に向けた教育・啓蒙型のチラシは、長期的に見込み客を育成する効果があります。また、こうしたチラシからLINE登録や資料請求へ誘導する仕掛けを入れることで、情報収集層との継続的な接点が作れます。
SNS・Webとの連動が「必須条件」に
スマホの普及により、チラシの役割は「紙で完結させる」ことではなく、“スマホで次のアクションを取らせる”ことが主目的になっています。
そのため、
- LINE公式アカウントへの登録導線
- InstagramやYouTubeのフォロー誘導
- モデルハウス見学予約のQRコード
- Web上の施工事例ページやお客様の声への誘導
など、オンラインへのスムーズな接続が、反応率に直結します。
特にLINEは、
- チラシ → LINE登録 → 自動返信で資料送付
- チラシ → LINEで日程調整 → 見学予約完了
といった即時性あるコミュニケーション設計が可能なため、多くの成果事例があります。
チラシ戦略も「時代に合わせて進化」させる
2025年現在、住宅検討者の行動は「紙で知り、ネットで深掘り、SNSで比較して、スマホで行動する」時代に突入しています。
チラシ集客を成功させるには、「ターゲットに合ったメッセージ」「比較・共感される価値の提示」
「デジタルへの自然な導線設計」という3点を軸に、チラシ戦略そのものを“アップデート”していく必要があります。
効果的なチラシの配布戦略とエリア設計
どんなに良いチラシを作っても、「届ける相手」と「届けるタイミング」を間違えれば、反応は得られません。成果を最大化するための配布戦略、エリア設計、タイミング設計の考え方を解説します。
配布方法の選択肢と使い分け
チラシの配布方法には、主に以下の4つがあります。
| 配布方法 | 特徴・メリット | 注意点 |
| 新聞折込 | 地域やエリアを絞って配布できる。高齢層にもリーチ可能。 | 若年層・非購読層には届きにくい。 |
| ポスティング | 新聞を取っていない家庭にも届く。配布範囲が柔軟に調整可能。 | 戸建・集合住宅で反応に差が出る。 |
| 戸建限定ポスティング | 注文住宅層に的を絞って配布できる。反応率が高い。 | 配布数が制限される。 |
| 店舗・施設設置 | 地元スーパー・ドラッグストアなど、生活圏内で接触できる。 | 自ら手に取ってもらう必要がある。 |
工務店にとっては、ポスティング(特に戸建エリア)との相性が良く、折込と併用するケースも多いです。
また、モデルハウス近隣や分譲地周辺など、商圏の“コアエリア”を重点的に配布することが成功の鍵になります。
|効果が出るエリア設計の考え方
成果を出すエリア設計は、「自社の強み × 商圏分析」で決まります。
1)まずは商圏分析を行う
- モデルハウスや施工現場のある拠点から半径5km〜10km圏内
- 直近の反響・成約者の住所傾向(Googleマイビジネス等でも確認可能)
- 土地価格・世帯年収・年齢構成の把握(国勢調査、RESASなど活用)
これらを踏まえて「反応が出やすいエリア」を抽出します。
2)ターゲット層がいるエリアを狙う
たとえば、共働き子育て世帯を狙いたい場合下記のエリアを狙うのが有効です。
- 小学校が近い
- 交通アクセスがよい
- 新興住宅地 or 開発が進むエリア
一方で、土地付き分譲がメインの工務店なら、下記の観点での選定も必要です。
- 土地価格が手ごろ
- 周辺にライバル物件があるか(比較優位が出せるか)
3)商圏別にチラシの内容を微調整する
商圏のニーズや家族構成によって、チラシの内容も変えるべきです。
- 学区訴求が刺さる地域 → 校区名入りのタイトル
- シニア多めの地域 → バリアフリーや平屋プランを強調
- 若年層が多いエリア → ローン相談やFP同席案内を強調
可能であれば、複数パターンのチラシを作成し、エリアごとに出し分けるのがベストです。
配布のタイミング設計
チラシ配布は「いつ出すか」で反響が大きく変わります。以下の3つのタイミングを意識しましょう。
① 週末前(木〜金)配布
もっともベーシックな手法です。
週末開催のイベント・見学会チラシは、木曜 or 金曜配布が基本。
このタイミングで配布することで、「今週末、見に行ってみようか」と行動につながりやすくなります。
② 給与日後(25日以降)
多くの家庭で「住宅ローンの支払いシミュレーション」や「資金計画」への関心が高まるタイミングです。
月末・月初に“家づくり”への意識が高まりやすい傾向にあります。
③ 行事・季節イベントに合わせる
- 春:新生活/入学・転校/子育て層の転居ニーズ増
- 夏:お盆の帰省・家族の将来を話す機会
- 秋:年内に住宅検討を始めたい層が増加
- 冬:ボーナス・年末年始に向けた家づくりの相談が増える
季節に合わせて「今動くべき理由」を盛り込むことで、反応率は大きく変わります。
配布後の反応を必ず分析・改善する
最後に重要なのは、配布したあとに反響をきちんと計測し、次回に活かすことです。
- 電話、LINE、Web予約それぞれの反響数
- どのエリアからの問い合わせか
- チラシのどの内容に反応があったか(聞き取り調査やQRクリック分析)
GoogleアナリティクスやLINE公式アカウントの統計データなども活用しながら、PDCAサイクルを回すことで、配布の精度と反応率が上がっていきます。
成功する工務店のチラシ集客戦略まとめ
ここまで、工務店のチラシ集客について、住宅購入検討者の行動変化や時代背景を踏まえた戦略をお伝えしてきました。最後に、成果を最大化するための7つのポイントに整理して、実践的に振り返ります。
ポイント1|「売りたい」ではなく「知りたい」情報を届ける
現代の住宅検討者は、「今すぐ家を建てたい人」よりも、「これから情報収集を始める人」が多数派です。
よって、チラシの内容も生活者の不安や疑問に応える情報を優先することで、信頼を得る入口になります。
- 「なぜ今建てるべきか?」
- 「住宅ローンの仕組み」
- 「土地探しの注意点」など
ポイント2|紙の役割は「きっかけ」づくりと割り切る
チラシは、スマホが当たり前の今の時代においては、情報を完結させるメディアではありません。
下記のような、「次のアクションへつなぐ仕掛け」が最も重要です。
- Webへの誘導(QRコード)
- LINE登録や予約ページへの導線
- SNSでの事例や口コミへの接続
ポイント3|ターゲットを絞り、メッセージを尖らせる
チラシは万人に向けて発信するのではなく、ニーズが明確なターゲットに向けてメッセージを絞り込むことが、高い反応率につながります。
- 子育てファミリー向け
- 2世帯住宅向け
- 平屋希望者向け
ポイント4|エリア戦略は「自社の強み」と「商圏の傾向」から設計する
単に「広く配る」だけではなく、
- 自社の施工実績が多い地域
- 競合との差別化ができる立地
- 土地価格や年齢層など、反応の出やすいエリア
に絞って、戦略的に配布することで、費用対効果が格段に上がります。
ポイント5|デジタルと連動した「チラシ+Webマーケティング」へ進化させる
2025年の今、紙媒体とWebを連携させることは“必須条件”です。
- チラシ配布後、WebサイトやLINEで情報補完
- SNSでのリターゲティング広告やリマインド配信
- アクセス・クリック率などの行動データ分析
など、紙で届けて、デジタルで深掘る体制を整えることで、反響を安定的に得ることができます。
ポイント6|見学予約・来場につなげる動線設計を
チラシの最終的な目的は、「問い合わせ」や「モデルハウス来場」につなげることです。
- イベントやキャンペーンで来場のハードルを下げる
- LINEで簡単に予約できる導線を設ける
- 来場特典・事前予約特典などのインセンティブを活用する
など、行動心理を考慮した“動線設計”が成果を分けます。
ポイント7|成果を“測定・分析・改善”して、次回につなげる
チラシは「出して終わり」ではありません。むしろ、
- どの地域で反響が高かったか
- どの訴求が最も効果的だったか
- どの導線から問い合わせがあったか
といったデータを集め、次回施策への改善に活かすPDCAサイクルを回すことが、中長期の集客力アップに直結します。
まとめ|紙だからこそ届く信頼と、進化する集客戦略を両立しよう
2025年現在、住宅業界はデジタル化の波の中にあります。しかしその一方で、「紙だからこそ届く信頼性」「地域との接点としての親和性」というチラシの価値も、まだまだ健在です。
大切なのは、紙とデジタルを対立させるのではなく、組み合わせて活用する視点です。
- 情報収集層には紙で興味を喚起し、
- デジタルで深く学び、
- モデルハウスで体験し、
- 営業が成約へと導く。
こうした一貫した体験設計の中に、チラシというメディアは今も重要な役割を果たしています。工務店の皆様がこの変化に柔軟に対応し、成果につながるチラシ戦略を構築できるよう、ぜひ本記事の内容をご活用ください。
来場予約を増やしたい工務店は株式会社ウィンクマークへ!
【超有料級】個別の無料マーケティング相談
住宅不動産業界の集客にお悩みの経営者様や営業責任者様、マーケティング部門の方に向けて、具体的な改善策や戦略をご提案いたします。広告予算の最適配分、来場予約の増加施策、自社集客の強化など、貴社の現状に合わせたアドバイスを無料で受けられる貴重な機会です。これまで数多くの成功事例を生み出してきたマーケティングのプロが徹底サポート。まずはお気軽にご相談ください!