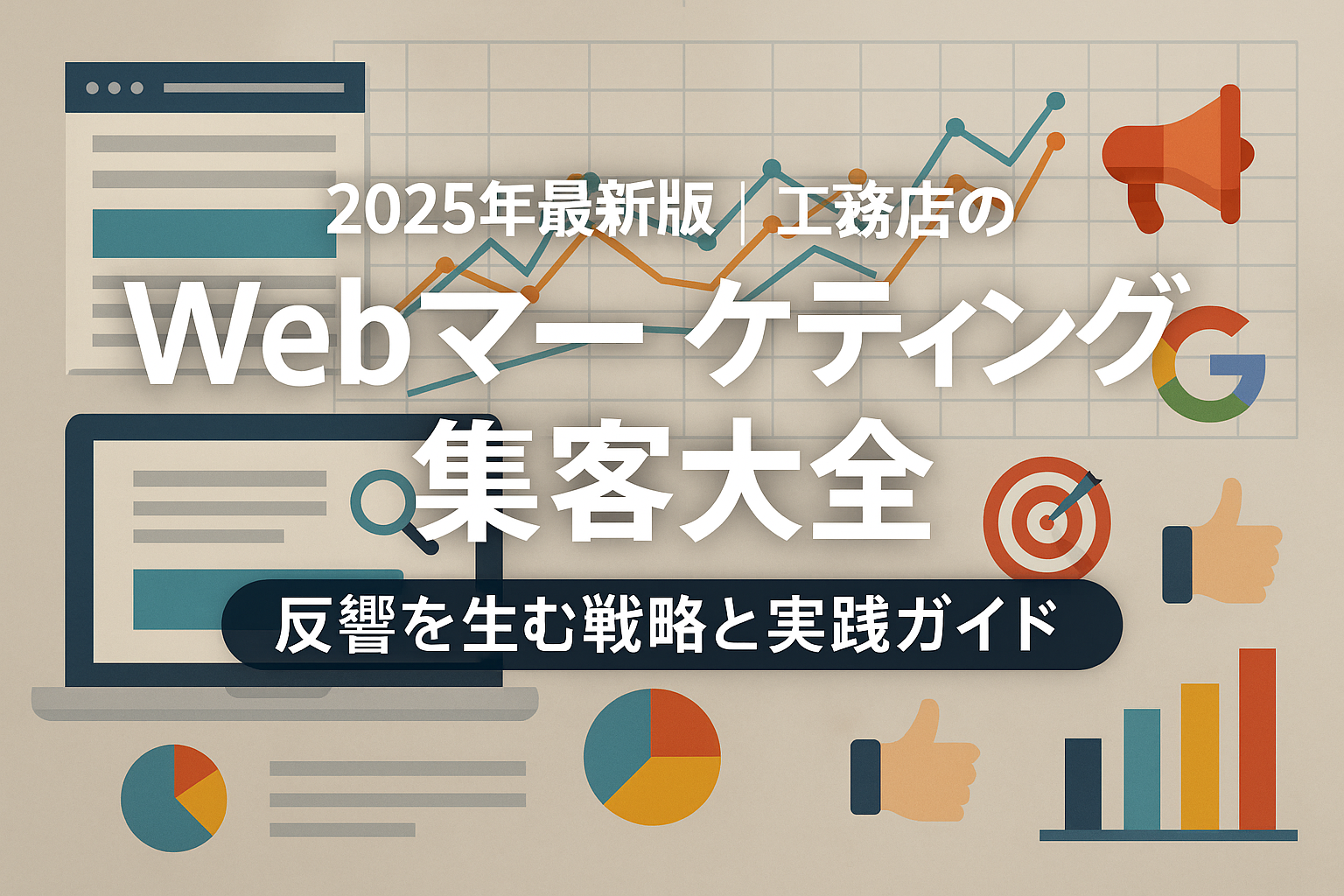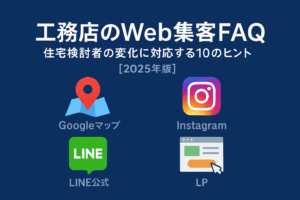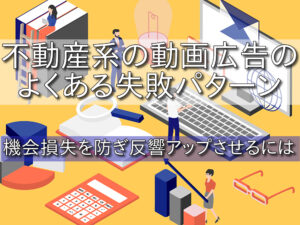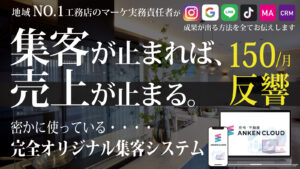住宅購入検討者の「情報収集行動」はこう変わった【2025年版】
近年、住宅購入を検討するユーザーの情報収集の方法は大きく変化しています。以前はチラシや住宅展示場、住宅雑誌などが主な情報源でしたが、2020年代に入ってからはWeb検索、SNS、Googleマップ、YouTubeなど「スマホ中心のオンライン情報収集」へと大きくシフトしています。
ここでは、政府機関や民間調査のデータを基に、住宅購入検討者が「どこで」「何を重視して」「どのように決定しているのか」を読み解いていきます。
1-1. 「スマホファースト」な住宅検討が定着
総務省の「通信利用動向調査(令和5年度)」によると、30〜40代のスマートフォン利用率は97.5%以上に達し、住宅情報の収集もスマホで完結するケースが大半を占めています。
また、住宅購入を検討し始めた段階で「まずWebで検索する」人が8割以上という結果が出ています。
🔍【データ引用】
総務省「通信利用動向調査(令和5年)」より
「スマートフォンを主に使用してインターネットを利用している割合は全年代で増加傾向」
つまり、現代のユーザーは「休日に展示場を回る前に、スマホで候補を比較検討する」ことが常態化しており、Web上での第一印象が集客を大きく左右する時代になっています。
1-2. 検討者は“情報の信頼性”を重視している
住宅という高額商材を検討するにあたり、ユーザーが重視するのは「実績」や「価格」だけではありません。特に注文住宅においては、
・実際に建てた人の体験談(口コミ)
・現場写真やルームツアー動画
・営業担当者の人柄が見える情報
といった「リアルな声」や「透明性ある発信」が判断材料となっています。
リクルートの「住宅購入・建築検討者調査(2023年)」では、住宅会社を選ぶ決め手として
「信頼感・親しみやすさ」が価格や性能よりも上位にランクインしています。
これにより、Webマーケティングにおいても「営業色の強い広告」よりも、「お客様の声」や「代表者の思い」「施工中の現場紹介」など人間味ある情報発信が求められているのです。
1-3. ユーザーは“複数チャネル”で同時並行的に情報を探す
現代のユーザーは、ポータルサイトや自社ホームページだけでなく、
・Instagramで施工事例を見る
・Googleマップで会社の口コミを確認する
・YouTubeでルームツアーを視聴する
・LINEで資料請求をする
といったように、複数のチャネルを使い分けて情報を探しています。
1-4. 「比較検討フェーズ」に入る前に候補から外れていることも
検索結果に出てこない
→ 見つけられない
→ 選択肢に入らない
→ 比較もされない
このように、ユーザーに見つけてもらう前に“無意識に除外されている”ことがWeb時代では多発しています。つまり、Webマーケティングとは単なる広告手段ではなく、「比較検討のスタートラインに立つための集客基盤づくり」だと捉える必要があるのです。
工務店の集客でWebマーケティングが有効な5つの理由
住宅業界、とくに地域の工務店においては、「やっぱりチラシや紹介が一番」と考えられてきました。しかし、2020年代のユーザー行動を踏まえると、Webマーケティングは今や欠かせない集客の柱です。ここでは、なぜ工務店にとってWeb集客が効果的なのかを、5つの観点から解説します。
理由①:検討初期から“情報接触”できる
ユーザーが住宅購入を検討し始める際、最初にとる行動は「ネット検索」です。これは、住宅展示場へ行く、モデルハウスを見る、といった実地行動よりも早い段階で行われます。
Webマーケティングを活用すれば、
・SEOやリスティング広告で「注文住宅 ○○市」などの検索に対応
・SNSやYouTubeで「家づくりの情報収集中」ユーザーへアプローチ
・Googleマップで地域名+ジャンル検索にヒット
というように、“検討しはじめたばかりの見込み客”にアプローチできるのです。
理由②:ユーザーの“興味・行動データ”が蓄積される
Webマーケティングでは、アクセス解析・広告反応・LINE登録・資料請求の履歴など、顧客の行動データが蓄積できます。これはチラシや紹介営業では得られない強みです。
たとえば:
・どのエリアの人がどのページをよく見ているか?
・どの間取りや価格帯に関心があるか?
・どの投稿が資料請求につながっているか?
といった情報を分析すれば、無駄な施策を減らし、反響率を高めるPDCA運用が可能になります。
理由③:集客の仕組み化(=“営業自動化”)ができる
Webを活用すれば、24時間365日、働き続ける“営業マン”を構築できます。
たとえば:
・「資料請求LP」+「LINE登録」+「自動ステップ配信」→ 来場前に教育・関係構築が進む
・「施工事例のSEO記事」+「MEOで見つけてもらう」→ 自然流入→問い合わせまで自動導線
このように、“人の労力に頼らずに反響を生む仕組み”が構築できるため、営業人員に余裕がない工務店にも最適です。
理由④:他社との差別化がしやすい
Web上では、自社の施工実績・コンセプト・設計力・対応力などを、写真・動画・文章で自由に発信できます。つまり、「デザイン」「性能」「土地提案力」「価格帯」など、自社ならではの強みをストレートに打ち出し、他社との差別化を明確にできるのです。
チラシでは1枚に詰め込む情報量が限られますが、Webでは
・事例別ページを多数作る
・営業担当者の紹介を載せる
・よくある質問を丁寧に書く
など、ユーザー視点で選ばれる理由を深掘りして伝えることが可能です。
理由⑤:“顧客の声”や“信頼”を資産化できる
Webマーケティングでは、
・Googleマップの口コミ
・Instagramでのお客様の声
・YouTubeでのOB施主インタビュー
・自社サイトの体験談ブログ
など、「第三者からの評価」が資産として蓄積されていきます。
とくに住宅は信頼性が命の商材。広告よりも「本音の声」「暮らしの実感」を参考にするユーザーが増えています。
一度良い口コミが増えれば、それが次の見込み客を引き寄せる“信頼の連鎖”となり、時間とともに集客力が強化されていくのです。
成果が出る!工務店のWeb集客手法7選【実践ポイント付き】
Webマーケティングは「やったほうがいい」と分かっていても、「何をどう始めればよいか分からない」という工務店も多いのが実情です。ここでは、現場で成果が出ている代表的なWeb集客手法を7つ厳選し、それぞれのメリット・注意点・実践ポイントを解説します。
手法①:SEO(検索エンジン最適化)
【概要】
Googleなどの検索エンジンで「注文住宅 ○○市」「平屋 間取り」など、ユーザーが調べるキーワードで上位表示を狙う集客手法。
【メリット】
・広告費ゼロで長期的に集客できる
・検討初期層に自然にアプローチできる
【実践ポイント】
・「地域+キーワード」でコンテンツを作成(例:「○○市で自然素材の家を建てるポイント」)
・施工事例、イベント情報、土地情報などをブログ形式で掲載
・定期的な更新(最低月2〜4本)
手法②:Google広告(検索広告・P-MAXなど)
【概要】
Googleの検索結果や提携サイト上に広告を出し、問い合わせや資料請求へと誘導する即効性の高い施策。
【メリット】
・特定キーワードを上位表示
・明確な効果検証が可能(クリック数・CV数)
【実践ポイント】
・「資料請求」「見学予約」など明確な導線を作る
・地域名や価格帯など具体的なキーワードを使う
・予算は月3〜10万円からでも運用可能
手法③:MEO(Googleマップ最適化)
【概要】
Googleマップや「地域名+業種」の検索で表示されるビジネスプロフィールを最適化し、地元ユーザーの来店・問い合わせを促す。
【メリット】
・地元ユーザーとの接点を獲得しやすい
・無料で始められ、費用対効果が高い
【実践ポイント】
・写真・投稿を週1ペースで追加
・良質な口コミをOB顧客から収集
・店舗名や説明文に「注文住宅 ○○市」などを自然に含める

手法④:Instagram・SNS運用
【概要】
施工事例・モデルハウス・スタッフ紹介などをビジュアルで伝え、ファン層を醸成する集客手法。
【メリット】
・“人となり”や“雰囲気”で選ばれる時代にマッチ
・LINEや予約フォームへの流入も可能
【実践ポイント】
・写真は「明るく、生活感のあるもの」が効果的
・ハッシュタグ「#○○市注文住宅」「#平屋の家」など地域×テーマで設計
・投稿だけでなくストーリーズ・リールで接触頻度を高める
手法⑤:YouTube/動画マーケティング
【概要】
ルームツアー・スタッフ紹介・家づくりの流れなどを動画で発信し、ユーザーの理解と信頼を深める。
【メリット】
・滞在時間が長く、関心の高い見込み客に響きやすい
・YouTubeからGoogle検索・SNSへの波及効果もあり
【実践ポイント】
・1〜3分程度の短尺動画からスタート
・「モデルハウス紹介」や「家づくりの流れ」は鉄板ネタ
・スマホ撮影+簡単な編集アプリで十分
手法⑥:LINE公式アカウントの活用
【概要】
資料請求・見学予約後のユーザーにLINEで情報を配信し、来場促進や関係性構築を行う。
【メリット】
・メールよりも開封率・クリック率が高い
・「ステップ配信」で自動的に案内が可能
【実践ポイント】
・資料請求完了後の“お礼メッセージ”を必ず設定
・来場までの案内・Q&A・施工事例などを段階的に配信
・イベント情報の告知にも効果的
手法⑦:コンテンツマーケティング(記事戦略)
【概要】
住宅購入に関する悩み・疑問に答える記事を継続的に発信し、検索流入と信頼を獲得する。
【メリット】
・指名検索(ブランド名検索)につながりやすい
・SEO効果・SNSシェアも見込める
【実践ポイント】
・ターゲット層の「疑問」をリスト化して記事化(例:「土地が決まっていないけど家づくりは始められる?」)
・1記事1テーマで深堀り
・月4本を目安に継続更新
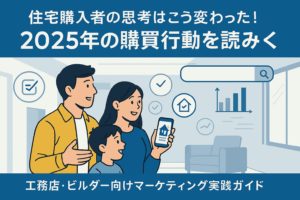
まとめ|組み合わせが成果を生む
Web集客は1つの手法で完結するものではなく、「SEO+MEO+SNS」「広告+LINE」など相乗効果を意識した組み合わせ設計がカギです。
| 手法 | 目的 | 即効性 | 継続性 |
|---|---|---|---|
| SEO | 自然流入 | △ | ◎ |
| 広告 | すぐに反響 | ◎ | △ |
| MEO | 地元からの集客 | ◎ | ◎ |
| SNS | ファン化・関係構築 | △ | ◎ |
| YouTube | 理解促進・信頼構築 | △ | ◎ |
| LINE | 見込み客の育成 | ◎ | ◎ |
| 記事 | 差別化・検索対策 | △ | ◎ |
Web集客の運用体制とツール活用【成果を出すための内製&外注バランス】
どれほど優れたWeb施策であっても、運用体制が整っていなければ成果は継続しません。
本章では、工務店が実際にWeb集客を行ううえで必要となる「社内体制」と「ツール活用」、そして「内製と外注のバランス」について解説します。
社内で持つべき基本の役割と考え方
Web集客の基本は「施策の企画」「コンテンツの作成」「数値の検証と改善」です。これらを社内で誰が担うかを明確にすることが第一歩です。
役割と担当の考え方
| 役割 | 内容 | 担当(例) |
|---|---|---|
| 戦略設計 | 何に力を入れるか月間目標は? | 経営者、マーケ責任者 |
| コンテンツ作成 | 施工事例・ブログ・SNS投稿 | 広報・営業スタッフ |
| データ分析 | アクセス数、CV率など | 外注 or 社内のマーケ担当 |
| 改善実行 | 投稿頻度調整・広告予算見直し | 全体の進行管理者 |
内製と外注のバランスはどうすべき?
Web施策はすべてを「外注任せ」にするのも、逆に「全部自社でやろう」とするのも非効率です。
✅ おすすめの役割分担の一例:
| 項目 | 内製 | 外注 |
|---|---|---|
| Instagram・SNS投稿 | ◯ (現場写真や日常投稿は社内が適任) | △(継続的な運用代行は可) |
| 施工事例ブログ | ◯(現場スタッフが内容を把握) | ◯(文章構成・SEO化のみ外注もOK) |
| Google広告運用 | △(専門性が高いため外注が安心) | ◎(少額から対応する業者も) |
| MEO対策 | ◯(写真投稿・口コミ対応は社内) | ◯(初期設定や戦略アドバイスは外注) |
| コンテンツ戦略設計 | △(定期的な見直しが必要) | ◎(伴走型コンサルがおすすめ) |
おすすめWebマーケティングツール
Web運用を仕組み化・効率化するための代表的なツールをご紹介します。
| ツール名 | 用途 | 無料プラン |
|---|---|---|
| Googleアナリティクス | アクセス解析 | ◯ |
| Googleサーチコンソール | 検索流入の分析 | ◯ |
| LINE公式アカウント | ステップ配信・顧客管理 | ◯(有料拡張あり) |
| Canva(キャンバ) | SNS画像作成 | ◯ |
| Notion / Trello | 投稿スケジュール管理 | ◯ |
| ChatGPT | 記事構成・キャッチコピー案 | ◯(無料でも活用可能) |
成果が出ている会社が共通して行っている「3つの習慣」
・毎月の振り返りを欠かさない
アクセス数・来場数・広告費用対効果などを記録・共有し、改善ポイントを見つける。
・“Webを使う目的”を明確にしている
「予約数を増やす」「来場前に教育する」など、施策の目的をはっきりさせ、スタッフも共有。
・社内ミーティングでSNS・ブログネタを出し合う
1人で考えるのではなく、現場・営業・設計など、全員でコンテンツの種を持ち寄る体制。
今すぐできるWeb施策チェックリストと行動計画【スタートアップ編】
ここまでの章で、Webマーケティングがなぜ工務店にとって重要か、具体的にどんな施策があるかをご紹介してきました。とはいえ「一度にすべては難しい」「何から手をつければいいか迷う」という方も多いはずです。そこでこの章では、明日からでも始められる“小さな一歩”の施策と、段階的に進める行動計画を提示します。
Web集客のスタートチェックリスト
まずは、自社がどこまでWeb集客に取り組めているか、以下のチェックリストで自己診断してみましょう。
| チェック項目 | YES / NO |
|---|---|
| 自社ホームページに「施工事例」が掲載されている | 〇 / ✕ |
| Googleマップに会社情報が登録されており、口コミが3件以上ある | 〇 / ✕ |
| Instagramアカウントを開設し、週1回以上更新している | 〇 / ✕ |
| 「○○市 注文住宅」など地域系キーワードで自社が検索結果に出てくる | 〇 / ✕ |
| LINE公式アカウントで、資料請求者にメッセージ配信している | 〇 / ✕ |
| 自社の代表・営業・設計担当の顔がWeb上でわかる(写真・紹介) | 〇 / ✕ |
3つ以上「YES」がつけば、Webマーケティングの基盤は整いつつあります。
3つ未満なら、次のステップに進むための準備から始めましょう。
ステージ別|Webマーケティング実行計画(3ステップ)
【ステップ1:基盤構築期(1〜2ヶ月)】
・Googleマップ(ビジネスプロフィール)の整備( 営業日・写真・口コミ依頼など)
・ホームページに「施工事例」「資料請求フォーム」を用意
・Instagramアカウント開設・週1更新開始
【ステップ2:発信強化期(3〜6ヶ月)】
・ブログやコラム記事の発信(月2〜4本)
→ 地域×間取り・素材・価格・家づくりQ&Aなど
・SEOの基礎対策(タイトル・見出し・内部リンク)
・Google広告 or MEO対策をスタート
【ステップ3:仕組み化・自動化期(6ヶ月〜)】
・LINEでのステップ配信設計
→ 「資料請求→見学案内→Q&A→イベント告知」など自動化
・Instagram→LP→LINEの導線設計
・YouTube or OBインタビューなど信頼を深める動画活用
Web施策は「1人でやらない」ことが成功のカギ
Web集客の失敗要因の多くは、「社内で担当者が孤立してしまう」ことです。
成功している会社は以下のような工夫をしています。
(1)営業・設計・現場でネタを出し合う「コンテンツ会議」を月1回開催
(2)社長がSNSやブログに積極的に登場
(3)専門家(広告代理店・SEOライターなど)と連携しながらPDCAを回す
つまり、会社全体が「伝える姿勢」を持ち、チームで取り組む姿勢が重要なのです。
無理なく継続するための3つのアクション
(1)1ヶ月ごとの“実行目標”を決める
例:「今月は施工事例を3件アップする」「Instagramを毎週更新する」など具体的に
(2)投稿ネタを“事前にストック”しておく
施工写真・お客様の声・スタッフ紹介など、社内で撮影・記録する習慣をつける
(3)効果が出ている内容は“横展開”する
Instagramで反応が良かった投稿内容を、ブログやLINEでも再活用する
まずは「見つけてもらう仕組み」づくりから
Web集客は短期的な効果を追うのではなく、“集客の地盤を作る行為”です。
「見つけてもらう」→「知ってもらう」→「共感される」→「選ばれる」
この流れを構築できれば、紹介や広告に依存しない“持続的な集客体制”が手に入ります。
来場予約を増やしたい工務店は株式会社ウィンクマークへ!
【超有料級】個別の無料マーケティング相談
住宅不動産業界の集客にお悩みの経営者様や営業責任者様、マーケティング部門の方に向けて、具体的な改善策や戦略をご提案いたします。広告予算の最適配分、来場予約の増加施策、自社集客の強化など、貴社の現状に合わせたアドバイスを無料で受けられる貴重な機会です。これまで数多くの成功事例を生み出してきたマーケティングのプロが徹底サポート。まずはお気軽にご相談ください!